親も子もドキドキの“初お弁当”

入園して間もなく迎える「初めてのお弁当の日」。
子どもにとっては
ワクワクと少しの緊張が混じる、
大きな一歩でもあります。
これまで
家族と一緒に囲んでいた食卓から離れ、
自分の力で「食べる」という経験を通して、
少しずつ自立の芽が育まれていくのです。
一方で、親の心境は複雑。
普段は目の前で食べさせている我が子が、
ちゃんとお弁当を開けて、
自分の手で食べられるのか、
残さず食べられるか、
友だちと一緒に楽しく過ごせるか…など、
心配が尽きません。
とくに幼児期は好き嫌いが激しかったり、
集中力が長く続かなかったりと、
食事の工夫が必要な時期でもあります。
そのため
「何を詰めるか」「どう詰めればよいか」は、
子ども目線での配慮が不可欠です。
本記事では、
筆者自身の体験をもとに、
子どもが一人でも
楽しく食べられるお弁当づくりのコツや、
あると便利なグッズ、
意外な落とし穴とその乗り越え方など、
リアルな情報を交えてご紹介していきます。
自分で食べられる工夫を第一に考えよう

我が家の息子が幼稚園に入園したとき、
一学期の前半は毎日お弁当持参の日々でした。
今では給食が始まっているのですが、
当時は「自分で完食できること」を目指して、
毎朝お弁当づくりに奮闘していました。
通っている幼稚園では、
なんとフォークもスプーンも禁止。
使用OKなのは普通の箸だけで、
補助箸(エジソン箸)もNG。
3歳で箸を完璧に使いこなせる子は少ないので、
自然と“手で食べやすい工夫”
が求められるようになりました。
ミニトマトや卵焼き、
ウインナー、ブロッコリーなど、
手でつまみやすく、
色合いも楽しいおかずを中心に用意しました。
ピックを活用しておかずを刺したり、
汁気をしっかり切って持たせたりと、
扱いやすさを意識した工夫も取り入れています。
子どもが「一人で食べられた!」
と感じられるよう、
詰め方やサイズにも配慮しました。
意外と難しい!ミニおにぎりのサイズ感

「おにぎりなんて簡単」
と思いがちですが、
実はとても奥が深いのです。
最初は大人の感覚で握っていましたが、
先生から
「もっと小さく、少なめにしてください」
と繰り返し指摘を受けました。
結果、たどり着いたのは
“大人のひとくちサイズ”の
小さなおにぎりを3つだけ詰めるスタイル。
ところがこのサイズ、
手で握るには意外と手間がかかります。
小さく成形しようとすると崩れやすく、
ラップで包むのも大変。
この「ちょうどいいサイズ」の
おにぎりを毎朝作るのが、
実は一番の悩みどころだったのです。
ダイソーで神アイテム発見!小さなおにぎりも楽々
そんなとき、
SNSで話題になっていた
100円ショップの便利グッズを思い出し、
ダイソーで
「ミニおにぎりメーカー
(商品名:ごはんがポン!ミニおにぎり型 3個用)」
を購入。
これがまさに救世主!
スプーンでご飯を型に入れて、
フタをして数回振るだけで、
きれいな一口サイズのおにぎりが3つも完成。
手が汚れず、失敗も少ないのでとても助かります。
さらに、息子自身が楽しんで
“おにぎり作り係”をしてくれるように。
振っているうちに
「もっと作りたい!」と
止まらなくなるほど(笑)。
できたおにぎりを小さくカットした
ラップやワックスペーパーで包めば完成。
見た目も可愛く、
食べやすさもバッチリです。
子どもが「食べきった」と感じられる量を意識
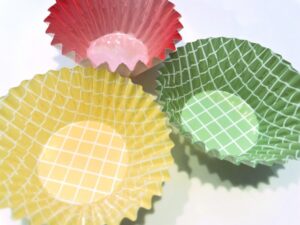
お弁当箱選びにも悩みました。
普通のお弁当箱ではサイズが大きすぎて、
全部食べきれなかったときの
“がっかり感”が強くなってしまうのです。
そこで我が家では、
小さめのフルーツ用ケースを使用。
そこにミニおにぎり3つと
おかず2~3品だけ詰めました。
偏食気味な息子にとって、
これが“完食できるちょうどいい量”
だったようで、
毎回空っぽにして帰ってくるようになりました。
子どもにとっては
「完食した!」という達成感が何より大切。
見た目以上に、
量の調整がとても重要だと感じました。
デコ弁は一旦お休み。まずは食べやすさ重視で
SNSで見かける、
猫や動物の顔になったおにぎり。
確かに可愛いけれど、
最初はそこまで頑張らなくても大丈夫です。
まずは“ちゃんと食べられること”を
第一に考えて、
見た目よりも実用性に注目するのがおすすめです。
それでも100均のピックやワックスペーパー、
シールなどを上手に使えば、
簡単に“映える”お弁当になります。
子どもが好きな
キャラのアイテムを選ぶのもポイント!
海苔パンチやマステで開け口をわかりやすく

おにぎりやおかずをラップで包む場合、
どこが開け口かわかるようにしておくと、
子どもがスムーズに食べられます。
例えば、
マスキングテープを貼ったり、
シールで目印をつけたり。
海苔用パンチで表情をつけるのもおすすめ。
パンダやくまなどのキャラ顔があると、
子どもも大喜びです。
うちでは
「白ご飯+海苔パンチ=パンダおにぎり」が定番。
ワックスペーパーでキャンディ包みにすれば、
可愛くて清潔、食べやすさも◎です。
詰め方のポイントと保冷対策も忘れずに
お弁当を詰める際は、
すき間ができないように工夫すると
型崩れ防止にもなり、
雑菌の繁殖を抑えることにもつながります。
小さなお弁当箱なら、
おにぎりとおかずを交互に詰めたり、
カップで仕切って安定させるのがポイント。
特に夏場は保冷剤も活用して、
上下を挟むようにセットすると効果的です。
仕切りカップやピック、デザインペーパーなど、
100均で揃うアイテムでじゅうぶん対応できます。
まとめ|お弁当作りは「続けられる工夫」から

ここまでご紹介してきたように、
小さめのサイズ感、食べやすい工夫、
子ども自身が楽しめる仕掛けなど、
ほんの少しの工夫を積み重ねることが、
無理なく続けられるお弁当作りにつながります。
毎日のお弁当づくりは、
見た目や華やかさよりも
“続けやすさ”と
“子どもが笑顔で食べられること”
が大切です。
理想のお弁当像にこだわりすぎず、
まずは親も楽しみながら、
子どもが自分で食べ切れる工夫を
少しずつ取り入れていきましょう。
完食した空のお弁当箱を見たときの嬉しさは、
きっと何よりのご褒美になります。


