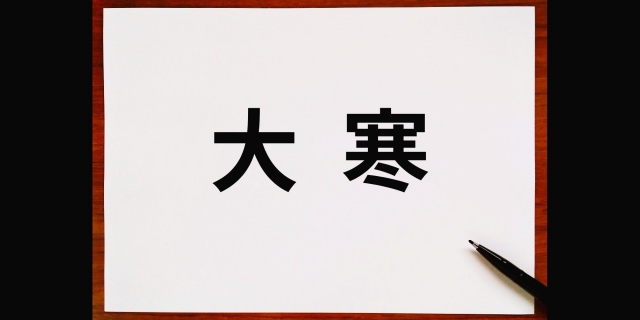「二十四節気(にじゅうしせっき)」という言葉は聞いたことがあるけれど、すべてを覚えるのは難しい…そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。「学校のテストに出たけれど思い出せなかった」「俳句づくりで季語として使いたかったけど正確な順が分からなかった」など、実際に困った経験がある方もいるかもしれません。
この記事では、二十四節気の基礎知識から覚え方のコツ、さらに季節にまつわる楽しみ方まで、実用的で楽しい情報をたっぷりお届けします。
二十四節気とは?基本の理解

二十四節気を理解するためには、まずその由来や仕組みを知ることが大切です。このセクションでは、二十四節気の歴史と気候との関係、日本での役割について、より深く掘り下げて紹介します。
二十四節気の意味と歴史
二十四節気とは、太陽の動きをもとに、地球が1年をかけて太陽のまわりを一周する過程を24に分け、それぞれに節気という名前を付けたものです。この考え方は紀元前の中国・戦国時代に暦の制度として発展し、漢の時代に現在のような24節気の体系が整いました。その後、遣唐使などを通じて日本にも伝わり、日本の自然風土に合わせた季節の指標として取り入れられるようになりました。
農作業のタイミングを示す指針としてはもちろん、漁業や祭事、衣食住の切り替えの目安としても機能し、旧暦とあわせて庶民の生活にも深く関わってきました。
二十四節気の仕組みと気候への影響
1年を約15日ごとの節目に区切ることで、二十四節気は季節の移ろいを細やかに捉える仕組みとなっています。各節気は太陽黄経(地球から見た太陽の通り道)に基づいて定められており、たとえば立春は太陽黄経315度、春分は0度、夏至は90度といった具合に決められています。
こうした節気は、春夏秋冬のそれぞれに6つずつ配分されており、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」といった季節の始まりを告げる節気や、「春分」「秋分」「夏至」「冬至」などの天文学的に重要な節気も含まれています。現代でも、農業だけでなく、気象予報や健康管理、行事の計画などに役立てられる知識です。
日本における二十四節気の重要性
日本の気候は四季がはっきりしており、梅雨や台風、積雪といった独自の気象現象があります。そのため、二十四節気は単なる古い知識ではなく、今の暮らしにも生きた情報として活用されています。
また、二十四節気は季語として俳句や短歌に取り入れられ、風流を楽しむ文化の一部としても根付いています。茶道や華道では季節の設えや献立に反映され、和の心を大切にする精神ともつながっています。
現代では「旬の食材」や「季節の暮らし」といったキーワードとともに、健康的で心豊かな生活を送るための指針として注目されることが増えてきました。忙しい日々の中でも、節気を手がかりにして季節の変化に気づき、生活に取り入れることで、自然との関係をあらためて意識し直すきっかけになるのです。
二十四節気の一覧とそれぞれの意味

ここでは、二十四節気を一覧で確認し、それぞれがどのような意味を持っているのかを具体的に見ていきましょう。日付だけでなく、どのような自然現象や行事があるのかを知ることで、季節の変化により敏感になれます。
二十四節気一覧とカレンダー
以下は代表的な節気とその目安日付と概要です:
- 立春(2月4日ごろ):春の始まり。草木が芽吹き、旧暦では一年のスタートとされてきました。
- 雨水(2月19日ごろ):雪が雨に変わり、氷が解け出す時期。農耕の準備が始まります。
- 啓蟄(3月5日ごろ):土の中で冬眠していた虫たちが目を覚ます頃。
- 春分(3月20日ごろ):昼と夜の長さがほぼ等しくなる日。お彼岸や先祖供養の風習もあります。
- 清明(4月4日ごろ):すべてが清らかで明るく、草木が成長する様子が顕著になります。
- 穀雨(4月20日ごろ):穀物を潤す春の雨が降る頃で、田畑の準備が本格化します。
このように、各節気には自然のリズムと生活の知恵が詰まっています。夏、秋、冬の節気についても同様に知っておくことで、1年を通して季節感のある暮らしが実現できます。
各節気の特徴と行事
それぞれの節気には、季節の移ろいを示す自然現象や行事があります。たとえば、立夏には田植えの準備、霜降では紅葉狩りなど、その時期特有の風習と結びついています。夏至には昼の長さを祝うイベントが、冬至にはゆず湯やかぼちゃ料理を楽しむ習慣が根付いており、日本の文化と深く関わっています。
また、節気を基にした行事には、端午の節句(芒種前後)や七夕(小暑の時期)などもあり、日常に取り入れることでより自然とつながる感覚が養われます。
七十二候にみる季節の移り変わり
二十四節気をさらに細かく分けた「七十二候」では、5日ごとの自然の変化を表現しています。例えば「鶯(うぐいす)鳴く」「蛙(かえる)始めて鳴く」「麦秋至(ばくしゅういたる)」など、詩的で繊細な季節の移ろいを感じることができます。
この七十二候の表現は、江戸時代には庶民の教養として親しまれており、現在でも和菓子の名や日本酒のラベルに用いられることがあります。こうした表現に触れることは、日常に季節の詩情を取り戻す一歩となるでしょう。
二十四節気を簡単に覚える方法

すべての節気を一気に暗記するのは難しく感じられますが、工夫次第で楽しく覚えることができます。ここではおすすめの3つの方法をご紹介します。それぞれの方法には向き不向きがありますので、自分の得意な感覚に合わせて選ぶのがポイントです。
覚え方歌で楽しく学ぶ
メロディーに乗せて節気を覚える「二十四節気のうた」は、子どもから大人まで楽しみながら記憶できる人気の方法です。学校や塾、カルチャースクールなどでも取り入れられており、歌詞に振り付けを加えることでさらに記憶に残りやすくなります。
たとえば、「立春・雨水・啓蟄・春分♪」という具合に、リズミカルな曲調で歌うと自然と口ずさめるようになります。親子で一緒に歌ったり、YouTubeの教材動画などを活用すれば、より楽しく学べるでしょう。
イラストやマインドマップで覚える
視覚的に覚えるのが得意な人には、イラストやアイコン、季節の風景と一緒に節気名を並べたマインドマップやビジュアルチャートが効果的です。たとえば、春には桜やつくし、夏には海やスイカ、秋には紅葉、冬には雪だるまなど、各節気に連想できるイメージを添えると記憶に残りやすくなります。
また、自分で手書きして作ることも大切です。脳は「書いたこと」を記憶しやすくなる性質があり、手で描くことで記憶の定着力が高まります。SNSなどで他の人のマインドマップを参考にして、オリジナルの学習ツールを作ってみましょう。
二十四節気の暗記法:語呂合わせ
たとえば「リッシュン・ウスイ・ケイチツ…」のように、音の響きやリズムを意識して並べると記憶に残りやすくなります。頭文字を取ってストーリー仕立てにするなど、自分なりの覚え方を工夫すると効果的です。
また、「春は立って雨が軽い(立春・雨水・啓蟄)」といったように、意味を含めた語呂合わせはイメージしやすく記憶が定着しやすいのが特徴です。グループ学習でクイズ形式にしたり、紙に書いて部屋に貼るのもおすすめです。
二十四節気にまつわる食べ物と行事

節気ごとに旬の食材や伝統行事があります。食と行事の両面から、二十四節気をもっと身近に感じてみましょう。ここでは、食文化と風習をより詳しく見ながら、それぞれの季節を彩る具体的な例も交えてご紹介します。
季節ごとの風習と食文化
二十四節気は、農作業や暮らしの区切りだけでなく、食べ物や行事とも深く結びついています。たとえば「春分」には先祖を供養するお彼岸の行事があり、ぼた餅をお供えする風習があります。「夏至」には関西地方を中心に、半夏生にタコを食べて豊作を祈願する習慣があります。
「秋分」では再びお彼岸を迎え、今度はおはぎを供えます。「冬至」には無病息災を願い、かぼちゃを食べてゆず湯に入るという、昔ながらの風習が今も根強く残っています。
また、地域ごとに受け継がれてきた伝統料理や、風習にまつわる行事食も豊富に存在します。九州では「立春大吉もち」、東北では「寒仕込み味噌」など、土地ごとに工夫を凝らした季節の味わいがあります。さらに、こうした行事食は子どもたちにとっても「季節を味覚で覚える」良い機会となり、家族の会話や学びにつながります。
二十四節気に対応した料理とレシピ
それぞれの節気に合わせて食卓を整えることで、暮らしの中に自然な季節のリズムを取り戻すことができます。旬の食材を意識するだけで、献立に変化が生まれ、自然と栄養バランスも整います。以下は代表的な節気に合わせた家庭でも作りやすい献立例です:
- 「立春」:豆ご飯や菜の花のおひたし
- 「小満」:新じゃがの煮物やそら豆の塩ゆで
- 「白露」:秋鮭の塩焼きやきのこご飯
- 「大雪」:おでんや鍋料理
こうしたレシピは、旬の食材を使うことで栄養も豊富になり、自然の恵みを体に取り入れることができます。スーパーで季節の野菜や魚介を選ぶ際に、「今が旬かどうか」という視点を持つだけで、料理の幅も広がり、日々の食卓がより楽しくなります。レシピ本や地元の食材コーナーを参考に、毎月1つの節気メニューにチャレンジしてみるのもおすすめです。
最新情報:2025年の二十四節気をチェック

毎年のカレンダーでは、二十四節気の日付に微妙な変化が見られることがあります。これは、地球の公転運動やうるう年などの影響によるものです。2025年も例外ではなく、節気の日付が前年と1日ほどずれるケースがあります。このズレを把握することで、年間の行事計画や暮らしの準備がよりスムーズになります。
また、天候や気温の変動により、実際の体感季節と節気のずれを感じることもありますが、節気を「季節を見直すきっかけ」として活用することで、自然とのバランス感覚を養うことができるでしょう。
二十四節気の更新情報とカレンダー
2025年の二十四節気は、地球の公転運動に基づいて例年と大きな違いはありませんが、数日のずれが生じることがあります。下記は2025年版の主な節気とその予想日付です:
【春の節気】
- 立春:2月3日(月)
- 雨水:2月18日(火)
- 啓蟄:3月5日(水)
- 春分:3月20日(木)
- 清明:4月4日(金)
- 穀雨:4月19日(土)
【夏の節気】
- 立夏:5月5日(月)
- 小満:5月20日(火)
- 芒種:6月5日(木)
- 夏至:6月21日(土)
- 小暑:7月6日(日)
- 大暑:7月22日(火)
【秋の節気】
- 立秋:8月7日(木)
- 処暑:8月23日(土)
- 白露:9月7日(日)
- 秋分:9月22日(月)
- 寒露:10月8日(水)
- 霜降:10月23日(木)
【冬の節気】
- 立冬:11月7日(金)
- 小雪:11月22日(土)
- 大雪:12月6日(土)
- 冬至:12月21日(日)
- 小寒:2026年1月5日(月)
- 大寒:2026年1月20日(火)
- 立春:2月3日(月)
- 春分:3月20日(木)
- 夏至:6月21日(土)
- 秋分:9月22日(月)
- 冬至:12月21日(日)
年間を通じて節気を意識することで、毎日の暮らしに季節の息吹が感じられるようになります。カレンダーアプリや手帳に書き込んでおくと、自然のリズムに沿った生活がしやすくなります。
年間行事の見直しと新たな習慣
節気は、単なる暦の区切りではなく、暮らしのリズムを整える重要な手がかりになります。2025年のカレンダーをもとに、生活の中に節気を取り入れてみましょう。季節の変化に寄り添うことで、無理のない自然な暮らし方が身につきます。
たとえば:
- 立夏からは冷たい料理を取り入れて体調管理を意識する
- 寒露から衣替えや寝具の見直しを始める
- 冬至に合わせて「ゆず湯」や「かぼちゃ粥」で風邪予防をする
また、節気ごとに家族や友人と小さな季節イベントを設けるのもおすすめです。「今日は霜降だから、きのこ料理を楽しもう」など、自然と食卓や生活に彩りが生まれます。
2025年は、こうした節目を意識して、日常の中に小さな楽しみや行動のきっかけを増やしてみてください。毎月1つの節気を目安に「新しいことを始める日」「家族と話すテーマを決める日」などにすると、1年を通じて自然の流れと調和した充実した暮らしが築けるはずです。
二十四節気を楽しむイベント紹介

全国各地で行われる二十四節気にまつわるイベントや、家庭でできる楽しい取り組みを紹介します。昔ながらの知恵にふれながら、家族や地域の人々と季節を楽しむ機会を増やしてみましょう。
各地での二十四節気イベント
近年では、二十四節気をテーマにした地域イベントが各地で開催されています。観光資源としても注目されており、地域の魅力を再発見するきっかけにもなっています。例えば:
- 【春分祭】(京都・3月):季節の花々を用いた献花式や、和菓子作り体験
- 【夏至のキャンドルナイト】(東京・6月):省エネをテーマにしたライトダウンイベント
- 【霜降の味覚まつり】(長野・10月):きのこや秋野菜の直売と郷土料理の試食
- 【冬至フェア】(岐阜・12月):ゆず湯体験と冬野菜の販売コーナー
こうしたイベントでは、地元の特産品や伝統文化に触れながら、二十四節気の意味や自然のサイクルを体験できます。開催地域によっては、歴史ある神社仏閣での祭事や、農業体験・郷土料理講座などを組み合わせたプログラムも充実しており、旅行と学びの両面から楽しめる内容となっています。
イベント情報は観光協会や市町村の公式サイトなどでチェックして、季節ごとの旅の予定に組み込んでみるのもおすすめです。
親子で楽しむ二十四節気の活動
家庭でも、二十四節気を取り入れた過ごし方を楽しむことができます。忙しい日々のなかでも、季節を感じる小さな遊びや手仕事を取り入れることで、親子の時間がより充実したものになります。
- 「立春」に:ベランダや庭に春の花を植える
- 「小暑」に:氷を使った冷菓やかき氷づくり
- 「秋分」に:月見団子を一緒に作って、お月見を楽しむ
- 「大寒」に:味噌仕込みや保存食づくり体験
また、七十二候を絵本で読む、季節の植物をスケッチする、旬の野菜を使った料理にチャレンジするなど、親子で季節感を共有することで、自然への関心や暮らしの豊かさを育むことができます。
こうした取り組みは、子どもにとっても「季節を感じる」実体験となり、記憶にも深く残るでしょう。さらに、自由研究や家庭学習の題材としても活用できるため、学習面にも良い影響が期待できます。
二十四節気を通じて季節を感じる

忙しい日常のなかでも、節気を意識することで自然のリズムを感じることができます。季節の移り変わりは、私たちの身体や心にも大きな影響を与えています。このセクションでは、季節を取り入れた生活の工夫をさまざまな視点からご紹介します。
四季の美しさを実感する方法
現代の暮らしでは、エアコンやLED照明に囲まれて、季節の変化を感じにくくなりがちです。しかし、二十四節気を意識することで、日々の中に小さな「季節のサイン」を見つけやすくなります。四季のリズムに敏感になることは、心の余裕を育み、自然とのつながりを深める第一歩です。
たとえば:
- 街路樹の変化に気づく(芽吹き、花、紅葉、落葉)
- 朝晩の空気の冷暖や湿度に注目する
- 季節の鳥や虫の鳴き声に耳を傾ける
こうした自然の変化を意識することで、心にゆとりが生まれ、四季の美しさをより深く味わえるようになります。散歩の途中に空を見上げたり、道端の草花に目を留めたりするだけでも、季節とのふれあいが生まれます。写真を撮ってSNSに投稿する、日記に自然の様子をメモするなど、自分なりの“季節観察ノート”を作るのも楽しい習慣になります。
二十四節気を利用した生活への取り入れ方
節気を取り入れた暮らしは、特別なことをしなくても始められます。むしろ、無理をしない「自然体の習慣」が、長く続けるコツになります。たとえば:
- カレンダーに二十四節気を書き込む
- SNSや日記に「今日は〇〇(節気名)」と記録する
- 季節の食材を意識して買い物をする
- 季節に合わせた掃除や衣替えのタイミングを決める
これらを習慣化することで、自然の変化を生活に取り入れながら、無理のない穏やかな暮らし方を築くことができます。
最初は一つでも構いません。気に入った節気を一つ選んで、その日に何か小さな行動を起こしてみるだけでも、生活に彩りが加わります。たとえば「今日は立秋だから、冷房を少し控えてみよう」「霜降なので、紅葉を見に行く計画を立ててみよう」といった意識づけだけでも、日々の暮らしが季節のリズムとともに心地よく暮らしていることを実感できるでしょう。
まとめ

二十四節気は、古代から現代に受け継がれる「季節を感じる知恵」の結晶です。
一見すると難しそうに思える名前や仕組みも、語呂合わせやイラスト、食文化といった身近な方法を使えば、ぐっと覚えやすく、親しみのあるものになります。
2025年の節気をカレンダーに取り入れて、日々の生活の中で季節の移ろいを感じてみませんか?
はじめの一歩として、こんなことから始めてみましょう:
- 自分の誕生日や記念日に近い節気を調べてみる
- その節気にまつわる行事や食べ物を試してみる
- カレンダーに節気の名前を書き込んでおく
- SNSや日記に「今日は○○」と書いてみる
小さな行動の積み重ねが、自然と寄り添う豊かなライフスタイルへの第一歩になるはずです。